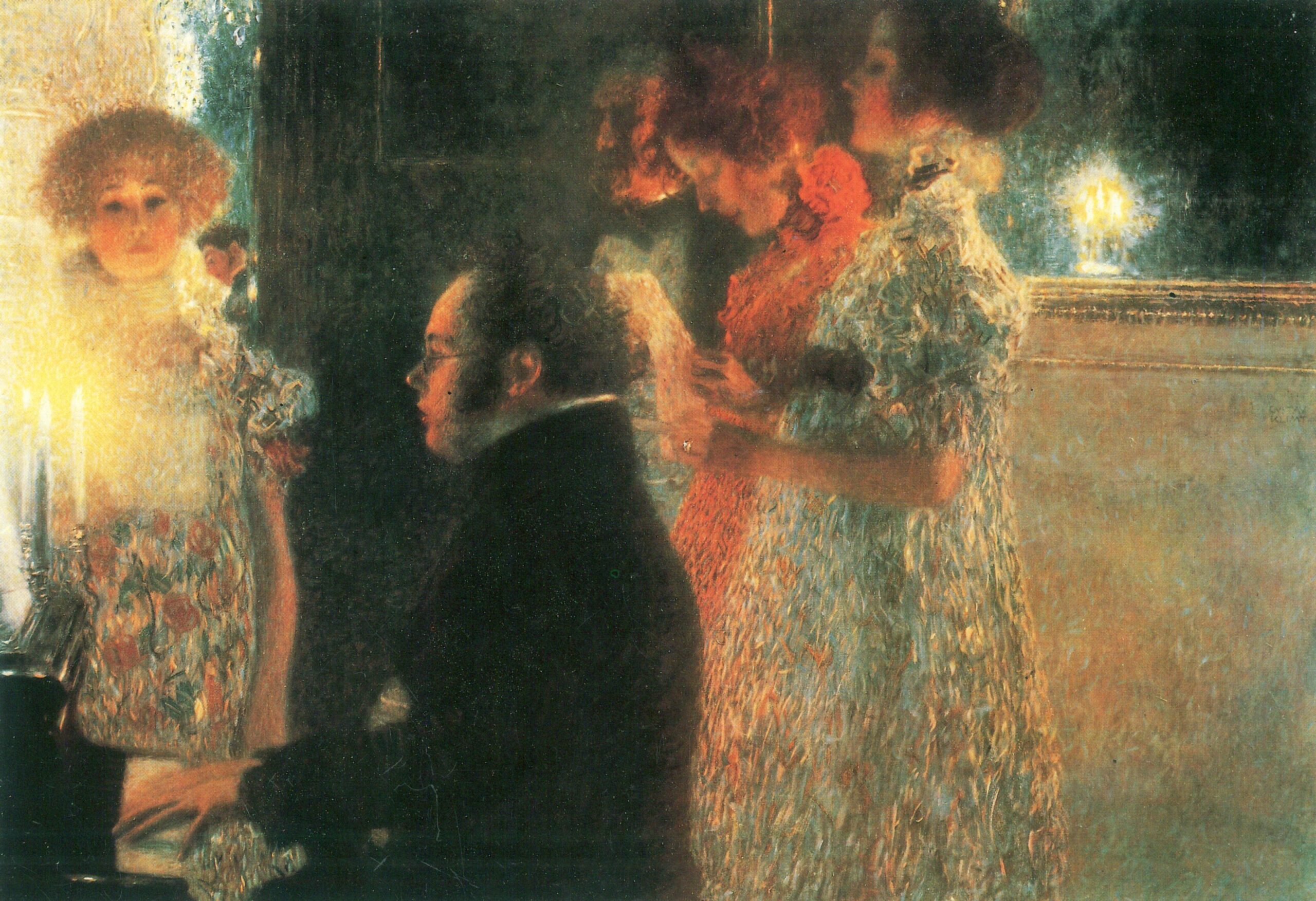一曲目の幻想ポロネーズから、目頭がにじんだ。予期しない涙だった。音色だとか、タッチだとかテクニックだとか、そういうのに感動して出た、涙ではない。まったく不意に、魂の底をつっと人差し指で押されて、こぼれた涙なのだ。母の友人が招待してくれたリサイタルである。バイト後、駆け込むようにして千代田線に乗り込み、火照ったカーディガンを脱ぎながら走って、開演三分前に席に着いた。遅くなったことを母の友人に詫び、久方ぶりの挨拶もそこそこに、演奏ははじまった。母たち二人は開演の二時間ほど前に、ラーメン屋で彼を見かけたと騒いでいた。
彼は舞台に入り、素朴なお辞儀をして、そっと幻想ポロネーズから始めた。二階席の右側に座る私、ピアノの蓋で見え隠れするピアニストの顔。サントリーホールがファツィオリの音を玉のように包んで、ひとつひとつ上へ押しあげていった、ため、二階席にも関わらずちょっぴり上を仰ぐようにして聴いていた。音はピアノそのものより、照明にほど近い空間から響いてきていた。
ややすると、労働の疲労が私を心地よい眠りに導いた。私はピアノのコンサートや映画館で、眠ることが作品や演者へのさしたる無礼や批判だとは感じていない。つまらないから眠るのではない。波長の同調、内臓ごと温泉にひたすような、賞賛の心地よさから微睡むのだ。しかしご招待で席に着けた身、直ぐ隣の母に小突かれて微睡みは立ち消えた。
教会での叫び声、窓に注がれる太陽、湖畔に踏み入る足音。楽譜の上に載せてしまえば同じラの音がそんな風に聴こえる。私の頭は勝手に物語を紡ぎ始め、音を追いきれないほどに目まぐるしく幻影が通り過ぎていく。響板から水が噴出し、二階席まで水浸しになって、鼻のあたりまで波が押し寄せる。彼は水中で演奏を続ける。ハンマーが泡をふきながら打鍵する。私は背浮きになり、天井を見上げると、いつの間にか夜のとばりに覆われて、照明は月になっている。耳に入ってくる水がひんやりと、鼓膜を冷やして、水中で奏でられる美しい音をひろう。
彼は弾きながらハミングしていた。一見愉しげで、実のところさみしい鼻歌だった。一片の悲しさもない鼻歌は、この世に存在しないことを思いだした。彼が森のなかで独り、朽ちたピアノを弾きながらハミングするのを想像した。その背中。何てさみしげで幸福に満ちているだろう。ピアノはいつも、こうやって湖や月や、森を私に連想させる。人前で弾くときは、そんな心持ではいられない。やはり私にとって、ピアノという美しい楽器と付き合うには、聴くか、独りきりで奏でるか、そのほかにはないようだ。
人前で演奏を続ける演者の労苦を、吐き気を、高揚を想った。そして拍手をおくった。ぬるい夜風、東京の軋みが、演奏の余韻を彩った。